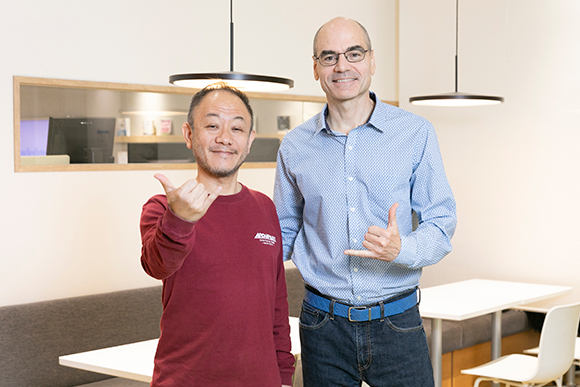社会を変えうる技術として注目が集まっているドローン。高所など人間がアクセスしにくい場所の点検・検査をはじめ、測量、農業、建設、荷物の運搬、災害救助など、幅広い分野での活用がますます期待されている。そうした未来の実現に向けて、開発者の努力が続いている。
2024年10月25-27日の3日間、ドローンの自動・自律制御ソフトウェア「ArduPilot(アルデュパイロット)」の国際開発者会議「ArduPilot Developers Conference」が、石川県加賀市で開催。最新技術のプレゼンテーションや、試作機を含む実機デモなどが行われ、大盛況のうちに幕を閉じた。
今回は、ArduPilotのコア開発メンバーであるRandy Mackay(ランディ・マッケイ)氏、そして同会議を主催したドローン・ジャパン株式会社 代表取締役社長の勝俣喜一朗氏にお話をうかがい、これまでオーストラリアで行われていた国際会議が、なぜ今回は石川県加賀市で行われたのか、会議ではどういった成果があったのか、詳しく語ってもらった。
ドローンを産業活用する切り札、自動・自律制御ソフト「ArduPilot」とは
今回の国際会議の主役であるArduPilot(アルデュパイロット)とは、オープンソースで提供されるドローンの自動・自律制御ソフトウェアだ。ドローンと言えば、ラジコンカーのように人間が目視操作するイメージが強いが、産業分野では無人操縦、自動操作・自律制御への関心が高い。それを実現するソフトウェアであるArduPilotは、品質の高さから近年幅広くエンジニアの関心を集め、採用が広がりつつある。
ArduPilotが対象とするのは、ドローン(UAV)だけではない。水上・水中ドローン、VTOL、タイヤで地上を走行するローバー、ボート、気球、さらにはロボットなども制御できる。また、オープンソースであるため、基盤システムの構築コストを抑えられること、信頼性の高さ、バグが発見された際の修正対応の速さも注目されている。
今回、石川県加賀市で開催されたArduPilot Developers Conferenceには、国内の関係者も含めると約100人が参加した。米国、カナダ、英国、オランダ、オーストラリア、インド、スウェーデンなど海外からの来訪者がその8割を占めたという。
今回お話を伺ったランディ・マッケイ氏は、ArduPilot開発者コミュニティの中核メンバーである。日本在住歴も長く、オーストラリア在住のAndrew Tridge(アンドリュー・トリッジ)氏と共に、開発者コミュニティを先導する立場だ。
「ArduPilot開発者コミュニティはオンラインで毎日のように議論や話し合いをしています。そんな技術者たちが、年に1回、実際に会って一年間の開発成果を発表し、最新技術を見せ合って未来について話し合う、参加者がとても勉強になる場がArduPilot Developers Conferenceなんです」(ランディ氏)
ちなみに、国際会議そのものの会期は3日間だが、メインの発表を行う開発者はそれに先んじて数日前に現地入りし、協力して集中的にプログラミングを行っている。その成果がすぐに会議で披露・共有されるオープンな雰囲気も興味深い点だ。
なぜ加賀市だったのか? 自治体の強力な後押し
ArduPilot Developers Conferenceは、前回までオーストラリアで行われており、今回が日本での初開催となる。日本で行うにあたっては、東京や大阪、名古屋などの大都市で開催するのが一般的だと思われるが、それがなぜ、石川県加賀市で行われたのだろうか。
勝俣氏はその理由として、毎年加賀市で行われているドローンエンジニア向けミーティング「ドローン・エンジニア会議 in KAGA」をあげた。加賀市の施設を拠点に、2泊3日のスケジュールでドローンについて学び、交流するためのイベントだ。
勝俣氏が社長を務めるドローン・ジャパンは、ドローンに関する様々なビジネスを手がけているが、中核的な事業と言えるのが技術者の育成・養成だ。2016年5月に「ドローンエンジニア養成塾」をスタート。ドローン(アルデュパイロット)の運用、アプリおよびファームウェアの開発技術を座学と実習の両面で学ぶのが特徴で、ランディ氏はその「塾長」として携わっている。2024年8月までに合計17期開催され、通算で675名の卒業生を送り出した。
ドローン・ジャパンはそうしたエンジニア育成の一環として、毎年7月に「ドローンエンジニア養成塾の出張特別講座」として行われているドローン・エンジニア会議 in KAGAに参画しており、それを発展させる形で、今回のエンジニア国際会議「ArduPilot Developers Conference」の開催に至った。
法制面でもドローン事業を支援する「加賀市フリードローン特区」宣言
そもそも、加賀市でこのような数々のドローンエンジニア向けイベントが行われる理由として、同市のドローンに対する積極的な取り組み姿勢がある。加賀市では、飛行許可などなにかと課題の多いドローンおよび関連ソフトウェアの開発を、民間企業と市が一緒になって支援する「ドローンコンプレックスKAGA」というモデルを展開している。
さらに加賀市は、今回のArduPilot Developers Conferenceの初日のセレモニーの場で、「加賀市フリードローン特区」宣言を行い、法制面でのドローン産業支援も打ち出した。
日本国内では、ドローンを巡って、電波法や航空法など、航空機に関する規制が数多く存在する。開発者は、私有地内などごく局所的な試験飛行であっても、所定の申請を行い、許可を得るまで待たなければならない。その作業は諸外国に比べて煩雑だ。こうした事態は、先端技術の開発気運を削ぐ恐れもある。
そこで加賀市では、「近未来技術実証ワンストップセンター」をこのほど市内に設立。ドローンや自動運転の研究開発にかかる手続きについて、ワンストップで行えるようにする計画を発表した。また、加賀市内の九谷ダム周辺では、ドローン運用で重要な5.8GHz帯電波の特例利用がまもなく承認される見込みとなっており、より高度なドローン技術の実証実験が可能になると期待されている。
「加賀市の宮元 陸市長から、『ぜひとも毎年加賀市で国際会議をやってよ』と積極的なアプローチをいただきました。その強いパッションとリーダーシップに感銘を受けています」(勝俣氏)
勝俣氏はドローンエンジニア養成塾を通じて「ランディのような世界のドローンオープンソースエンジニアと日本のエンジニアをつなげ革新的技術を産み出したい」という思いを常日頃から持っている。日本で国際会議を開催することで、より多くのエンジニアが世界から日本に集まり、交流が生まれる。それによって、また日本発の世界に向けた技術やビジネスのアイデアも生まれてくると期待している。