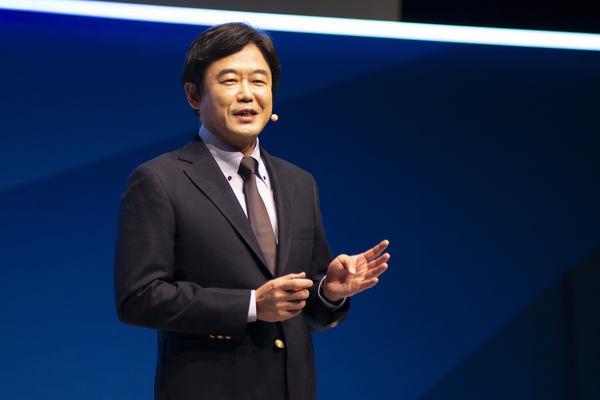KDDIスマートドローンは2025年5月29日、ドローン事業者や点検事業者、地方自治体などを対象としたカンファレンス「KSD CONNECT 2025」を開催した。制度整備、地域創生、人材育成、異業種連携など、ドローンビジネスの社会実装に不可欠なテーマが多角的に議論された。
本稿では、KDDI松田浩路代表によるオープニングセッションを皮切りに、KDDIスマートドローン 博野雅文代表、MODE 上田学CEO、大林組 小俣光弘氏、インプレス 河野大助氏によるパネルディスカッションの内容を中心に、同イベントの模様をレポートする。
KDDI松田代表が語る1,000拠点構想と地方実装戦略
KDDIの松田代表はカンファレンスの開幕に登壇し、「ドローンは空飛ぶスマートフォンだと思っている」と述べ、センサー、カメラ、通信、バッテリーといったスマートフォンに類似する要素を備えたドローンの将来性に早期から着目していたことを明かした。
KDDIは2016年にスマートドローン事業を立ち上げ、完全自律飛行、自治体との連携配送、ドローン航路の整備などを推進。2022年にはKDDIスマートドローンを設立し、制度整備と歩調を合わせながら日本航空(JAL)やSkydioとの資本提携を通じ、社会実装を加速させている。そして、「世界初・国内初の取り組みを開拓者として積み重ねてきた」と語る姿に自負をにじませた。
インフラの老朽化、災害多発、過疎地における物流網の維持といった深刻な社会課題に対し、ドローンは解決の中核を担うテクノロジーとして注目しているという。KDDIはその一環として、石川県と防災DXに関する包括連携協定を締結。災害発生時に即応可能なドローンの地域常設配備を視野に入れた体制構築を進めている。
| ▼石川県とKDDIが包括連携協定、Starlinkやドローンを活用したローソンの地域防災拠点化を検討 https://drone-journal.impress.co.jp/docs/news/1186688.html |
さらに、通信インフラとAIを融合した分散型AIデータセンターの整備、米Skydio製ドローンによる常設型ドローンポートの導入を通じて、遠隔からの即時運航・監視体制の実現も目指している。これにより、災害対応や定期点検などで“無人・即応・高精度”を可能とするインフラが形成されつつある。
松田氏は、「通信とAI、そして現場に根差したオペレーションを融合させることで、持続可能な社会貢献のループを確立したい」と語り、技術基盤と地域社会をつなぐプラットフォーマーとしての役割を強調した。
また、松田氏は「全国に1,000か所のドローン拠点を整備すれば、10分以内に現場対応が可能になる」と試算。KDDIが提供する衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」をドローンに活用し、「通信・AI・共創によって、ドローンを含む新たな社会像の実現に挑戦していく」と力強く語った。
災害・物流・人材育成を主に築く“運用可能な社会インフラ”
続いてKDDIスマートドローンの博野代表が登壇し、「社会実装のリアル 現場から見えるドローンの未来」をテーマに講演した。
これまでの実績として、約70の自治体、そして460社との連携、累計2,000時間・1万回超の飛行を実施してきたと述べ、「通信とドローンを組み合わせ、新たな社会価値の創造に取り組んできた」と振り返った。
続けて博野氏は、秩父市における土砂崩落現場や能登半島地震時の運用を例に挙げ、ドローンを活用した緊急対応の有効性を実地データに基づいて紹介した。その上で、2024年11月には、ドローンポートの設置から遠隔運航のオペレーションまでを包括的に提供する運用サービスを正式に開始したと述べた。
| ▼KDDIスマートドローン、ドローンポートを活用した遠隔運航サービスを開始 https://drone-journal.impress.co.jp/docs/news/1186751.html |
また、ドローン実装における人材面の課題にも言及し、全国21か所に展開する「KDDIスマートドローンアカデミー」において、即戦力として現場投入可能なオペレーターの育成プログラムを展開していると説明。操縦技能に加え、運航管理、データ解析、法令遵守までを網羅したカリキュラムによって、実務レベルの人材供給体制を構築している。
さらに、社会インフラとしてのドローン運用高度化を目的とし、Skydio社との戦略連携に基づく次世代ドローンポート「Skydio Dock for X10」をカンファレンス当日の5月29日より注文受付を開始したことを発表し、今夏からの国内提供開始にも言及した。
同ポートに格納される遠隔自律型ドローン「Skydio X10」は、非GPS環境や夜間においても高精度な飛行とデータ収集が可能であり、石川県警による行方不明者捜索や、首都高速道路での橋梁点検といった先進事例において、その性能が実証されている。
博野氏は、「Skydio X10は、災害対応やインフラ点検の運用を根本から変える“ゲームチェンジャー”に成り得る」と強調し、社会実装に向けた次世代運用モデルの可能性を提示した。
次に、2024年12月にはKDDIスマートドローンはMODE社との業務提携を通じて、生成AIを活用した次世代現場支援プラットフォーム「BizStack Assistant」の本格展開を開始した。同ソリューションは、現場作業者からの自然言語による“問い”を生成AIが理解し、関連するセンサーデータや映像を即座に収集・可視化することで、意思決定の迅速化と現場対応の最適化を実現していくという。
博野氏は、「生成AIとドローンを統合することで、従来は属人的だった判断や作業プロセスを自動化・標準化できる。現場対応のスピードと精度を飛躍的に高め、ドローンの社会インフラ化をさらに一段進めたい」と述べ、テクノロジー融合による実運用高度化への意欲を示した。
人手不足とインフラ老朽化が深刻化!ドローンで変える建設現場の“次世代管理”
ドローンジャーナル編集長の河野氏の進行のもとパネルディスカッションが実施された。大林組の小俣氏が建設業界における深刻な人手不足とインフラ老朽化への対応課題について、「熟練技能者の減少と、バブル期入社世代の大量退職が目前に迫る中、急速に老朽化が進む社会インフラを限られた人的リソースでいかに効率的かつ持続的に維持・管理していくか、それが現場における最優先かつ本質的な課題である」と指摘した。ダムの維持管理における現場では、ドローンとデジタルツインを活用した管理手法を導入しているものの、オペレーターの育成やデータ活用の標準化が障壁となっていると語った。
MODEの上田氏は、「BizStack Assistant」の開発背景に、多機能システムの乱立と現場DXの限界があるとし、「生成AIは気軽に操作できる部下のような存在」と解説。
実際の導入例としては、広大な建設現場において、AIアシスタントとドローンを連携させ、従来人手で行っていた巡視・点検作業の大幅な省力化に成功したケースを紹介。特に、物理的に固定カメラの設置が困難な現場においては、「ドローンという移動可能な“空飛ぶセンサー”こそが、可視化と即応性を両立する最適なソリューションである」と強調した。
博野氏は、「現場ニーズと蓄積してきたドローンの映像データとの間にギャップがあった」とした上で、MODEとの連携によって意味のあるデータ提供が可能になったと述懐。また、警備、夜間監視、アナログ計器の読み取りなど、ドローンの活用範囲が着実に広がっている現状を語った。
小俣氏は「ドローンサービスは社会インフラとして定着する」と述べ、AIとの連携により少人数でも高度な現場管理が可能になる未来を示唆。上田氏は「やがて“ドローンに話しかけて作業を依頼する時代”が来る」と今後の展望を述べた。
博野氏は「小規模な現場でも近隣の拠点からドローンが即時対応できる社会基盤を整備する」と語り、能登を皮切りとした全国展開、StarlinkとSkydio X10との連携を進めていく姿勢を明らかにした。