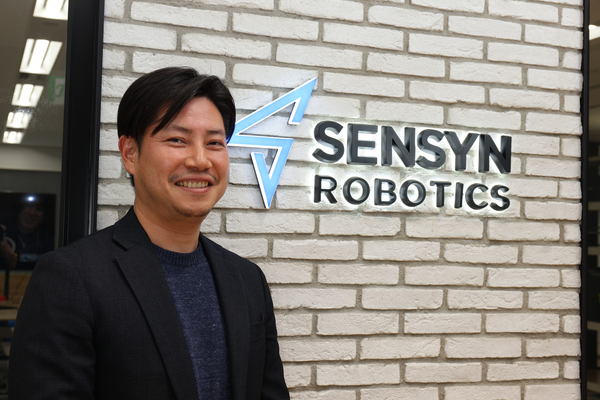ドローン関連企業の代表に最新の取り組みや業界に対する想い、経営の考え方などについてインタビューを行う当連載。第6回は、約5年前より自らの意思決定として「CSV経営(Creating Shared Value)」を推進してきたという、センシンロボティクス代表取締役社長 CEOの北村卓也氏にインタビューした。
センシンロボティクスは、同社独自のAI技術が組み込まれたアプリケーション開発プラットフォーム「SENSYN CORE(センシン コア)」を中核として、さまざまな分野で社会課題解決のためのソリューションを提供している。現在の従業員は約110名で、このうち3分の1以上がエンジニア、最も多いのはAIとロボットのエンジニアだ。「SENSYN CORE」の開発には、これまで資金調達した多くを集中投下してきたという。
「当社はドローン企業ではない」と断言する一方で、PoC(実証実験)だけでも700件以上の実績を持ち、これまで提供してきたソリューションの半数以上でドローンを活用する、ドローン業界でも注目度の高い企業だ。独自の路線でひた走る北村氏に、経営戦略やその想いを聞いた。
「ドローンだけでは不十分」——センシンロボティクスの本質
──「ドローン企業ではない」という理由を教えてください。
北村氏:誤解を恐れずに言うと、私自身もドローンは大好きなのですが、同時に「それだけではお客様の課題を根本的に解決することは難しい」とも感じています。なぜかというと、これは皆さんも実感するところかと思いますが、「ドローンだけでは解決できない部分が多すぎる」からです。そのため我々はソフトウェア企業として、3つのレイヤーから成るアプリケーション開発プラットフォーム「SENSYN CORE」を設計して、ソリューション開発を行ってきました。
1つ目がエッジの技術です。ドローンやロボットを人間がコントロールしている限り、運用はその人のリテラシーや絶対数などに依存し、人手不足が加速する現代日本において、それでは社会課題に対抗できません。そこで我々は、ドローンを含むさまざまなスマートデバイス群を、誰もが安心安全にコントロールし、動かすことができる「SENSYN Edge」を開発しました。
2つ目がデータ管理です。自動でデータを大量に取得できるようになっても、それを人間の目でチェックするのでは、逆に工数が増えてしまいます。そこで我々は、画像、映像、温度などの取得データを、ただアップロードして保有するのではなく、時系列でまとめる、地図と紐付ける、三次元化する、撮影位置情報などのメタ情報を埋め込むといった機能を持つ、「SENSYN Data」を開発しました。要は、取得データの高付加価値化を図り、「使える」状態で管理する仕組みです。
3つ目が、AI解析です。データの蓄積によってビッグデータになったものに対してAIを活用することで、異常や変状を検出し、そこからさらに予防保全や計画修繕などの意思決定支援につなげていきます。当社では「SENSYN AI」と呼び、コアテクノロジーとして位置付けています。
──AIとデータを活用したソリューション企業ということですね。
北村氏:そうですね。ただ、データ解析さえしっかりできれば現場の課題を全て解決できるかというと、そうではないと考えています。ポイントは、そのデータを「誰が使うか」です。ユーザーのITリテラシーに関わらず「誰もが使いやすい」UI/UXを目指し、業務アプリケーションの開発も手がけています。
と申し上げると、「技術力があるのは分かったけど業務理解はできているのか」とご質問をいただくことがありますが、確かに我々だけでは力不足なので、業界のトップランナーとの共創を大切にしています。彼らから真の課題感ならびに業界のしきたりやレギュレーションなどを学びながら、我々からは失敗も含めたノウハウや技術の提供を行うという、“Win-Winの等価交換”を通じて、アプリケーション群を作り込んできました。
何より重要なのは、データをいかにユーザーにとって使いやすくできるか。当社はもともとロボットの自律制御やGCSの開発からスタートしましたが、現在ではデータの利活用に注力してバリューを発揮したほうが、ビジネスインパクトとしても大きいと感じています。
──ソフトウェア企業ということで、機体は作らないのでしょうか?
北村氏:一部、ハードウェアも開発しています。ドローンやUGVなどの機体に、課題解決に向けて各種センサーを載せたいというお客様には、カスタマイズして差し上げる必要があるためです。ただし、ハードウェアの開発はスピードと資材調達、そして価格の観点から、基本的には市中に存在する汎用的なハードウェアのカスタマイズです。
「CSV経営」と業界大手との協業戦略
──御社の注力領域について教えてください。
北村氏:最初はほぼあらゆる業種をターゲットにしており、PoCだけで累計700件以上行ってきたのですが、その取り組みから割り出したのがインフラ関連の業務です。顧客の産業領域としては、産業インフラ系や社会インフラ系が中核で、加えて製造業や鉄道などがあります。業務領域としては、施工管理、点検・保全、巡視・監視の3カテゴリーが多いです。
というのも、我々は約5年前より、経営方針として「CSV経営」を掲げており、社会貢献性と経済性をバランスさせることを大事にしています。これを両立できる領域として、インフラ関連の業務にフォーカスしようと決めたのです。
──「CSV経営」とインフラ系へのフォーカスについて、具体的にお聞かせください。
北村氏:CSVとは、Creating Shared Valueの略で、簡潔に言えば「社会貢献性と経済性を両立する取り組み」です。私が考える「経済性」とは、「お客様が必要性を感じ、すぐにでも取り組みたい、対価を払ってでも導入したい」ことで、そうなると必然的に、人手不足や、作業が危険である、老朽化が著しいなどの理由で、「人手は減っていくが、ライフラインの確保としてやるべきことが増える」傾向にあるインフラ系が、我々のターゲットとなります。
また、我々は補助金をほとんど活用していません。補助金は、あくまで戦略的な成長や社会的連携を後押しする一つの手段と捉えています。当社が重視しているのは、事業の持続性と市場性であり、自立的な収益モデルの構築に力を注いでいます。「社会貢献性のあることをやって、きちんと収益も生み出し、自分たちも豊かになって、よりクリエイティブで社会にとって良いことをやりたい」と思えるような、最大公約数を目指していきたいと考えています。
ちなみに補助金も一部は活用していますが、例えば、国が進める方針に適合していくことでプレイヤーを増やす、マーケットの拡大を図るといった、マーケティング的な位置付けです。
──CSV経営を成立させるための戦略として、業界トップランナーとの協業を推進してきたということですね。
北村氏:はい。石油関係ではENEOS様、電力関係なら中部電力パワーグリッド様、建設関係なら竹中工務店様というように、業界別に大手企業と一緒にソリューション開発に取り組んできました。我々にとってはロイヤルカスタマーであり共創パートナーとして今後も関係性を大切にしていきたいと考えています。
彼らとのさまざまな取り組みの中で、ドローンを活用するメリットがある場合は、当然積極的にドローンを使いますし、絶対に墜落が許されないエリアもたくさんあるので、その時はドローン以外の技術を用いて、業務の無人化・省人化や高度化、いわゆるDXを推進しています。
最近の大きな変化でいうと、最初は点検や保全といった「お客様の業務からすると、大変重要だけれどもできる限りコストをセーブしたい」領域の案件から始まりましたが、そちらで価値を証明できたことによって、より本業に近い領域の業務もご一緒できるようになってきました。お客様1社あたりの活用領域が広がってきたことで、億単位の大規模ビジネスも生まれております。
──2024年には、中部電力パワーグリッドと御社の「ドローンを用いた送電設備点検技術」開発グループが、共同で「第69回澁澤賞」を受賞されました。
北村氏:そうなのです。澁澤賞は、民間の電気保安関係表彰として各界より認められている権威ある賞なので、非常に感慨深いです。これまで、中部電力パワーグリッド様と共同開発した本技術は、送電設備点検業務アプリケーション「POWER GRID Check」に実装されて、2021年から各電力会社向けに提供が開始されており、直近では同社と共同で送電設備異常を自動で検出するAIを開発、設備点検業務で導入しているところです。こうした動きはさまざまな業界で進めてきており、今後も生成AIなどの最新技術を活用しながら加速していく予定です。
日本のドローン業界の課題
──ドローン業界では、改正航空法や免許制度などの整備が進みましたが、どのような変化がありましたか?
北村氏:率直に申し上げると、慎重に捉えています。面倒になったと感じているお客様も非常に多いです。もちろん、産業が成熟していくにあたってルールが整備され、それに則った運用をしていくこと自体に異論はありません。特にドローンは、そのリスクの高さがゆえということも理解できます。しかし、市場が大きくなるより前に、ルールが先行してしまい、逆にマーケットを縮小させる要因になっていると感じています。実際に、「昔はもっと自由にできたのに」と言われたこともありますし、法改正をきっかけにドローンの導入を見送られたお客様もいらっしゃいます。
でも、当社のソリューションの多くでドローンを使っていますし、やはり存在感はありますよね。あとポテンシャルも高いと評価されています。ですので我々は、ドローンではカバーできないところまで含めて、最終的にお客様が達成したいことを最短最速で一緒に成し遂げるということに、コミットしています。
──ある意味、改正航空法が逆風になってしまっている中でも、御社のソリューションの多くでドローンが活用されているということですね。御社ならではの工夫があるのではないでしょうか?
北村氏:レベル3.5は追い風になっているのと、我々のお客様はもともとの安全意識が非常に高く、現場も通常は第三者立入禁止なので、そのような一般とは異なる環境下や条件下でドローンを用いるという前提に立って、ドローン活用の自動化をご提案したり、とっつきにくく感じられる部分をフォローさせていただき運用のハードルを下げるといった工夫をしております。